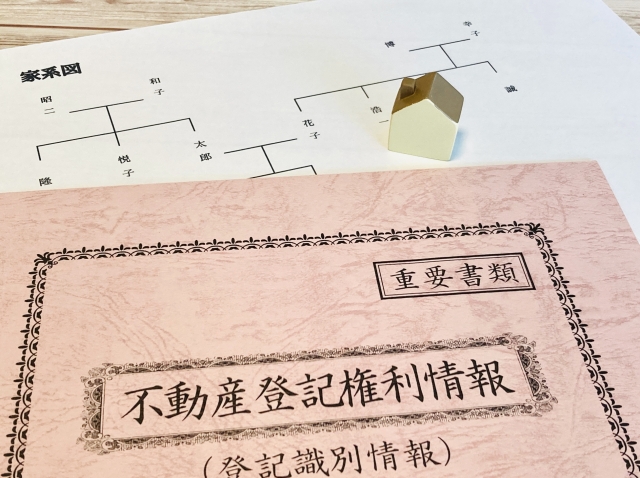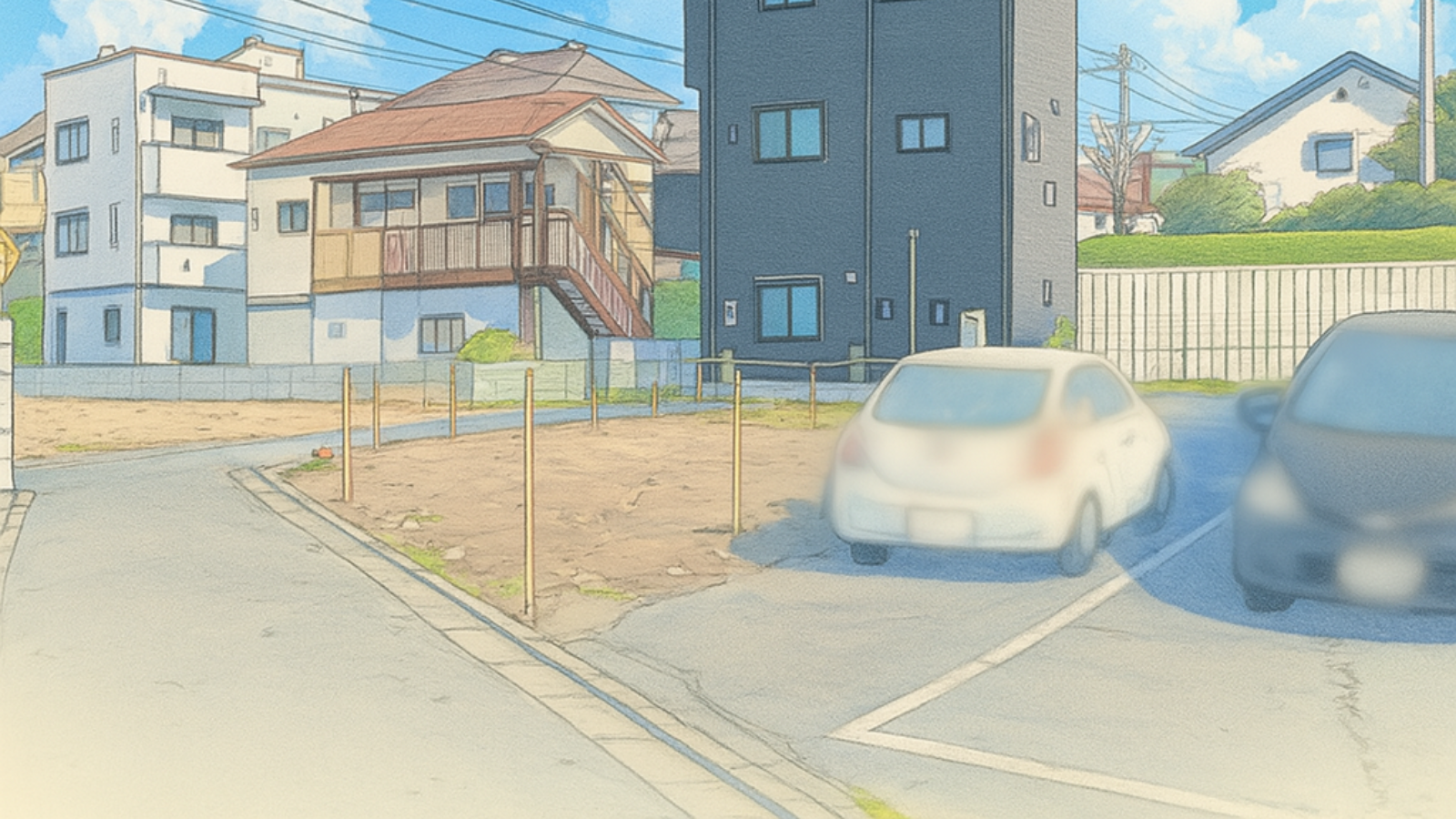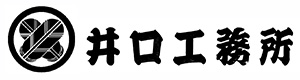工場の閉鎖や移転に伴い、跡地の売却を検討されるケースは少なくありません。しかし、工場跡地は「土壌汚染対策法」の対象となる可能性があり、通常の土地売買とは異なる専門的な知識と対応が求められます。私たちは、土壌汚染の調査から浄化、そして売却までをワンストップでサポートし、お客様の資産価値を守ります。
なぜ工場跡地の売却は難しいのか?
- 高額な調査・浄化費用:汚染の範囲や種類によっては、数千万円以上の費用がかかることもあります。
- 買主の契約不適合責任への懸念:買主は、購入後に汚染が発覚した場合の責任を懸念し、購入をためらいます。
- 融資の困難:金融機関が土壌汚染リスクを嫌い、買主への融資を断るケースがあります。
- 風評被害:「汚染された土地」というイメージが、売却をさらに困難にします。
e不動産屋の解決フロー
- 無料相談・履歴調査:まずはお客様の状況をヒアリングし、登記簿や過去の資料から土地の利用履歴を調査します。
- 専門調査会社との連携:信頼できる土壌調査会社と連携し、法令に準拠した正確な調査を実施します。
- 最適な浄化方法の提案:調査結果に基づき、コストと期間を考慮した最も効率的な浄化計画をご提案します。
- 行政協議・各種手続き代行:都道府県や市町村との協議、各種届出などを代行し、お客様の負担を軽減します。
- 汚染を前提とした売却戦略:浄化後の売却はもちろん、汚染がある状態のままで購入を希望する専門業者への売却など、多角的な出口戦略を検討します。
よくあるご質問 (FAQ)
Q. 調査費用はどのくらいかかりますか?
A. 土地の広さや調査内容によって大きく異なります。地歴調査だけであれば数十万円から可能ですが、ボーリング調査などが必要な場合は数百万円以上かかることもあります。まずはお見積もりをいたしますので、お気軽にご相談ください。
Q. 汚染が見つかったら、必ず浄化しないといけませんか?
A. 法律で浄化が義務付けられるケース(要措置区域の指定)と、そうでないケースがあります。また、土地の利用方法によっては浄化が不要な場合もあります。売却戦略と合わせて、最適な対応をご提案します。
Q. 相談だけでも可能ですか?
A. もちろんです。ご相談は無料です。まだ売却を決めていない段階でも、将来のために現状を把握しておきたいというご相談も歓迎いたします。秘密厳守で対応いたしますので、ご安心ください。